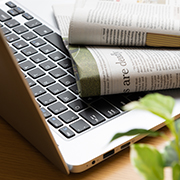1981~1987年
第7章 米国での現地生産開始、多角化の進展

- 第1節 創立50周年と世界メジャーへの第一歩
- 第2節 ファイアストン社・ナッシュビル工場買収
- 第3節 CI実施と社名変更
- 第4節 経営トップ新体制に
- 第5節 新たな市販用タイヤ市場への対応
- 第6節 タイヤ事業の国際化の進展
- 第7節 タイヤ開発技術の革新
- 第8節 多角化事業の推進
- 第9節 新たなる経営目標の明示
第4節 経営トップ新体制に
第1話 進展する国際化に向けた新体制
1985年2月、江口禎而副社長が代表取締役会長に、家入昭副社長が代表取締役社長に就任しました。石橋幹一郎会長は取締役名誉会長に、服部邦雄社長は取締役相談役に就任しました。
第2話 原価企画活動と体質改善活動
1985年、プラザ合意を契機とする円高が始まり、2年間でドルの価値が1ドル250円から125円と半分になり、輸出採算が悪化しました。このため、国内のダントツ体制の確立と、社内の体質強化が一層重要となり、体質改善活動が推進されることになりました。
原価企画活動の導入
商品企画、設計、製造、販売の各部門を巻き込み、原価企画委員会が組織されました。商品開発の初期段階のコスト管理の充実と、利益体質の強化、すなわち損益分岐点の引き下げを図るために、会社全体を1つの原価企画の対象として捉え、コスト戦略が展開されました。
QZD活動
1988年、「QC、QAの徹底により一切の欠陥商品を作らない、出さない体制を構築する」方針が出され、デミング・プラン推進部に「QZD※推進室」を設置。「思考・行動の原点を『ZD』に置き、過去の延長線を超えた体質を作る」との視点に立ち、活動を推進しました。
※Quality Zero Defectの頭文字をとった呼称。
JIT(ジャスト・イン・タイム)推進
「JIT体制」では、生産から販売に至る業務を直結し、顧客ニーズにスピーディー、フレキシブルに対応する体制を作り上げました。
市販用タイヤの物流ルートは、工場から支店倉庫を経由し、販売会社の営業所、小売店へと多段階構造になっていました。この中で、支店倉庫を経由する物を減らし、工場と営業所を直結するパイプを太くすることで、在庫と納期を圧縮することができました。また、物流業務は、本社、工場、支店に分離していたものを工場に統合しました。販売変動に生産がフレキシブルに対応することができるように、「4日先フリー」という、4日先であれば生産計画が変更できる体制も作り上げました。
その結果、在庫削減、間接部門の人員削減、リードタイム短縮、在庫照会、納期回答の時間短縮と精度向上、欠品解消期間の短縮など、多くの効果を生みました。
間接部門の業務改革と人事ローテーション
「業務改革」では、戦略課題を明確にし、業務をゼロベースで見直し、従来の陣容の70%で遂行できる体制を指向しました。成果への寄与の低い業務は必要でも切り捨て、創出した人材を開発・戦略業務に傾斜配置しました。そして、この「業務改革」と併行して、職能間、職能内の人事ローテーションが積極的に推進されました。