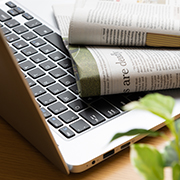1937~1949年
第3章 第二次世界大戦下の経営と戦後経営の基盤

第3節 敗戦による混乱と戦後の新体制
第1話 戦争による被害と生産再開
生産の再開
1945年8月15日、第二次世界大戦は日本の敗戦によって終結しました。国内の経済活動はほとんど機能停止の状況に陥っていましたが、当社は石橋社長の指示のもとで、いち早く生産増強と技術の近代化に取り組みました。
当社の敗戦による損害は、戦時補償の打ち切り、すべての海外事業の喪失など、総額約7,000万円に上りました。これは1945年の売上高4,358万円の1.6倍に相当します。
東京・京橋の本社は1945年5月25日の空襲によって全焼し、罹災後は麻布区飯倉片町(現港区六本木)に移転することになりましたが、久留米、横浜の両工場はほとんど無傷のまま終戦を迎えることができました。
主力工場は残存したものの、需要は激減し、敗戦の混乱の中で将来の経営の見通しをつけることは大変難しく、大幅な人員整理もせざるをえませんでした。1944年末時点で在籍していた従業員4,156名を、終戦とともに1,910名に減員しています。また、海外事業所からの引揚者は、従業員280名とその家族を合わせて800名で、全員の引き揚げが完了するまでには約3年を要しました。
久留米工場は、終戦から2ヵ月足らずの早さで生産を再開しています。これは、工場が戦災を免れたことと、安全な場所に疎開させていたタイヤの生産設備を終戦後直ちに工場に戻し生産再開に当てることができたこと、また戦時中に軍需用として割り当たられた天然ゴムやコードなどの原料を豊富に在庫していたことなどが幸いしたお陰です。
製造設備に大きな被害を受けた他社に対して、当社は被爆を免れた工場があり優位な生産再開となりましたが、他社も1945年秋から翌年春にかけて生産を順次再開。1946年下期の自動車タイヤ生産シェアは、当社が48%、横浜護謨が31%、中央ゴム(ダンロップ)が15%となっています。
タイヤ以外の製品では、石炭増産のためにゴムベルトの需要が増大しました。原料割当面でも優遇されたこともあり、当社はベルト生産専門工場を建設し、1946年5月からコンベヤベルト、平ベルトの生産を開始しています。
自転車産業への進出
自転車産業への進出は、石橋社長が希望していた自動車製造への足がかりとして、また民生復興上の必要性も考慮して決定したものです。旭工場では、1946年8月から自転車の試作を開始しましたが、長い歴史と経験を持つ既存メーカーとの技術格差は大きく、性能面でも生産性でもなかなか及ぶものではありませんでした。
苦境打開のために工場首脳部が着目したのは、フレームの各パイプの組み立て方法を改良することでした。1950年、当社は自転車工業では初めてとなるダイカストを利用したフレーム組立てに成功し、この組立法で国内外の特許を取得しています。従来法と比較すると、精度の向上、軽量化、外観の優美さ、設備の簡略化、低コストなど効用は大きいものでした。
旭工場はこれに先立つ1949年10月、ブリッヂストン自転車株式会社として独立しています。

米軍タイヤの修理
1948年、当社は駐留米軍から自動車用古タイヤの再生加工を委託されました。1949年3月、東京・赤羽に新鋭機械が設備された米国の大修理工場が設けられ、米国人技術者が指導に当たりました。1950年夏以降は、朝鮮動乱で生じた古タイヤも加わって、繁忙を極めることになりました。ピークとなった1951年3月の月産量は1万7,000本を超え、従業員も800名を数える時期がありました。
1957年9月、米軍との契約が満期を向かえ赤羽工場は閉鎖されましたが、当社が修理したタイヤは累計100万本以上となり、大きな利益につながりました。また米国の進歩した再生加工技術と更生タイヤ用の未加硫トレッドゴム(キャメルバック)の製造技術を学ぶことができたことがなにより大きな収穫となりました。
労働組合の結成
1945年夏に日本に進駐した連合軍は、日本の社会秩序を民主的なものに変えるための改革を進めました。その中で1945年12月に「労働組合法」、次いで1946年9月には「労働関係調整法」が制定され、日本国内では労働組合が次々と結成されました。
このような状況の下で、当社にも労働組合結成の気運が盛上り、1946年1月15日、久留米工場に全従業員が集まって組合結成総会が開催され、日本タイヤ従業員組合が結成されました。
1946年3月7日には、当社、日本ゴム、旭製鋼所の3社の従業員組合はアサヒ従業員組合連合会を結成し、労働協約締結と待遇改善に関する要望書を会社側に提出しています。社会的混乱とインフレのもと、総収入の3倍引き上げを要望していた組合側に対して、会社側は賃金と現物給与の合計で3倍に引き上げると回答し、労働協約については一部を修正して合意に至りました。
第2話 本格的な戦後復興へ
日本ゴムとの完全分離
戦後の日本では、連合軍による三井、三菱、住友などの財閥解体が進められました。日本ゴムと当社を支柱とする石橋一族も地方財閥とみなされ、解体の対象となることは必至でした。この動きを察知した石橋社長は、独占禁止法の実施も見通し、兄の徳次郎、弟の進一と協議の上、1947年2月20日をもって、日本ゴムと当社の完全分離を断行しました。当日、徳次郎、進一両家保有の当社株式と正二郎保有の日本ゴム株式を交換し、正二郎当社社長は同年10月、日本ゴム社長を辞任しています。
昭和天皇の行幸
当社は1949年5月28日、久留米工場に昭和天皇をお迎えしました。
その日のことを振り返り石橋社長は「じつに創立以来の光栄であった。この行幸は単なる産業奨励のためではなく、人間天皇として一人でも多くの国民に接して、日本再建のために働く国民の士気を高めるかたわら、戦争のため犠牲となった国民に対し、深い同情のお言葉をかけられ、真心にふれあうという御思召しだったので、我が社は工場内外の整理整頓はもとより、形式にとらわれず、ただ誠心誠意御歓迎申し上げることにしたところ、御到着にあたり、全従業員の中から期せずして歓呼の嵐がどよめき、日頃主義主張を異にする者すら国旗をふる姿が見られ、至情のほとばしりに感銘深いものがあった」(『私の歩み』)と回想していました。
お迎えの行事の計画は、工場整備を始め、その一切の段取りが石橋社長の指示のもとで進められました。戦時中に防空のため黒く塗られていた外壁は白く塗り替えられ、工場内部も十分な手入れが行われました。行幸を機に工場内外の戦時色は一掃されることとなりました。